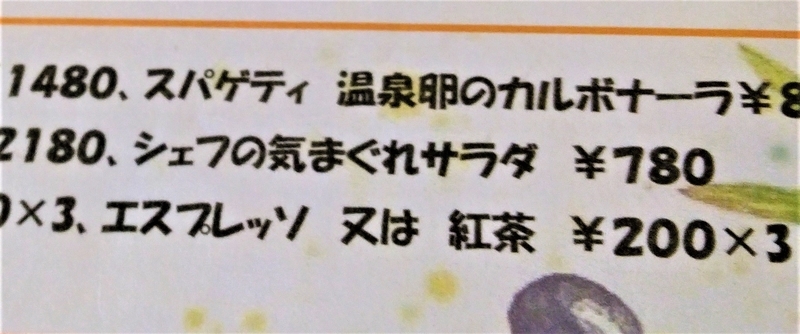「PLAN75」という映画をAmazonプライムで観た。
75歳以上になったら、特に健康上の理由がなくても、希望すれば安楽死を選択できるという、国の制度の話だ。
もちろんフィクションであり、ある種のファンタジーだけど、予告編を見た時は、これってセンセーショナルな話となり、国会とかで取り上げられ、学校教育の場でも取り上げられ、なんて僕はちょっと考えていたが、実際には、国会と言えばAmazonプライムで観れるようになった今だって、1回も出席せずにクビになった人がどっかの国から帰って来るとか来ないとかの話くらいしかなく、この作品が教育現場に持ち込まれて議論されるといった事もこれまでなかったみたいだ。
「なんだか現実に十分にありそうで、怖いよね、世の中、ますます世知(せち)辛くなって来たしね」
ということで、終了である。
というのに驚いた。
なんだぁ、結構、みんなもう諦めムードなのかな?
食い詰め老人なんて僕たちの時代には半数くらいはそうなってそうだから、ウン、もう命の尊厳なんて言っている場合じゃなくて、とっとと合法的に処理しちゃいましょう、という世の中が来るのは、僕たちは若い頃から想像し、覚悟していた。「どうせ自分たちが老人になった頃には世の中そうなるぜ」ってみんなが覚悟していたから、今さらそんな映画を観たって、だよね、で終了なのかもしれない。
一方で、既に老人となっている人たちは、もしこれを見ても、その頃には自分たちは逃げ切った後の話だから、「これからの人たちは、年をとってからも、本当に大変だわねぇ」で終了なのかもしれない。(病院の待合室でよく聞く言葉だ)
さらに一方で、その頃には社会の中心となっていて(中年になっていて)、「処理する側」となる今の若者たちは、この映画を観て「なんだか面倒くせぇなぁ、散々食い散らかして、食い散らかされた後のゴミの山を、将来、俺たちが金払って処分するのかよ」って、ウンザリしているのかもしれない。
という殺伐とした状況にあって、あっさりこの作品はスルーされて行くのかもしれない。
というのに驚いた。
自分の感覚がすっかりズレてしまっているのだろうか?
人生は厳しく、みじめさの中でだらだらと生きねばならないなら、自らの意思で死を選択したい、なんて普通の話だ。そして世の中は需要と供給の調整で出来ており、需要が高まれば、そいういう選択をサポートする制度やサービスが生まれ、それを法的にも担保し、倫理的にも裏打ちする世論が出来上がるのだって、自然の流れだろう。
が、人間の不合理さとか気まぐれを、我々は本当に理解できているだろうか?
そんな覚悟がある?
長い夜が明けて現れた朝の日の光を見た瞬間、どんな苦しい状況にあろうと、そしてそれがこれからも続いて行く状況であろうと、「まだ生きよう」と力が湧いてくるあの不合理さを、つまり、単に朝の太陽を見たという事実だけなのに、生きる意味がまた新しく立ち現れる不思議さを、或いは、たった一人の身内の死体を見た時、その無念を晴らす為に、それまで築いて来たあらゆるものを投げ捨てて相手を殺せてしまえる強固な狂気を、つまり、単に一個の息をしない有機物を見たという事実だけなのに、なんの痛みも罪悪感も恐怖も感じず復讐すべき相手の腹にナイフを突き立ててしまえる、そんな人間という生き物の気まぐれを、僕たちは本当に理解しているのだろうか?
人間の不合理さや不思議さは、自然の流れに逆らい、気まぐれに世の中を大きく変えて来たのである。それとも無機質なネット社会の延長にあって、もはや1+1=2でしかなく、このまま老人となって行く僕たちは、生産性の低いゴミとして焼却されて行くのだろうか?1+1=10,000とかにはならない?
なんてな事を考えているうちに、会社では期末決算に向けた地獄のような資料作成と、部下の評価面談、今年度の振り返りと来年度の組織目標策定と報告、なんて毎晩深夜まで働いて、大丈夫、管理職は年俸制で組合なんて関係なく残業し放題だから、という具合にあっという間に1か月が過ぎて行ってしまった。
僕たちはこうやって忙しさの中で生を忘れ、死を忘れ、ある日突然、宣告を受け、病院のエントランスを後にしながら「マジかぁ、死ぬのかぁ、あっという間だったなぁ、何十年も生きたけど、結局何だかよく分かんなかったなぁ、とにかく痛いのは嫌だなぁ」なんて思うのかもしれない。
20年以上前、学生時代に銀座の映画館にわざわざ行って「セブン」という映画を観た時、まぁ銀座で観るような映画でもなかったが、主人公のサマセット刑事がエンディングのナレーションで語った次の言葉が印象に残ったのを覚えている。
「ヘミングウェイはかつて書いた。”この世は素晴らしい。戦う価値がある”と。後半には賛成だ」
そりゃ素晴らしいなんて言えるほどこの世はお花畑ではない。が、戦う価値がある、というコトバは、未来のある若者の心には刺さったのだ。平凡な話である。そう、「それでも戦う価値がある」という意味は、1+1=2の世界を人間の愛と尊厳で、なんとか1+1=10,000にするんだ、そこに人間という特別な生き物が存在する意味があるんだ、という西洋の神様から生まれた発想である。
そしてその反対側にあるのが方丈記の無常観だ。「世の中、1+1=2だよ。どうせね。それでいいじゃん」という発想である。かつて若者だった男が年齢を重ね、未来の時間がだんだん少なくなり、結局1+1=10,000に出来なかったけど、結構いろいろあって楽しかったな、最近、体のあっちこっちにガタが来てるし、涙もろくなったし、通勤途中の沿道にポツリと離れて咲いた桜の花につい感動しちゃうんだよな、なんてオジサンになると、「それでいいじゃん」に傾いて行くのである。
で、「PLAN75」だ。
自身の命も含め、不必要なものを誰も傷つけずに処理するのは「それでいいじゃん」という1+1=2の発想だ。一方で、いやいや違うでしょ、そんなんじゃ人間の愛と尊厳の意味がないでしょ、あり得なくない?という怒りは、それでも1+1=10,000にして見せる、というサマセット刑事の静かな怒りの境地である。
そして、この映画の主人公のように、1+1=2なんだし、自然の流れでPLAN75に申し込んで、とっとと死なせてもらおうと思ったけど、やっぱり何だか違うなって思って逃げ出して、だからって1+1=10,000なんかにならないのは知っているし、もはや「価値がある」なんて戦ってみせるだけの力は残ってないけど、目の前に映る朝焼けがあまりにも美しく、山の空気は新鮮で美味しく、世界がこんなに美しく見えるから、とりあえず生きよう、という気まぐれの力が、僕たちの生の根本にあるのでは?という事である。
そう、だから、僕たちは、人間の不合理さとか気まぐれを本当に理解できているだろうか?と思うのだ。
ところで、病院の話になったのでついでに、、、簡単な外科手術をするために数日だけ入院した。
初めての入院だったし、簡単な外科手術だから遠足気分だ。不謹慎極まりない話である。
ヨシ、買っただけで読んでいない本をこの機に読むぞって張り切って持って行ったら、入院手続きを済ませるや否やすぐに会社から電話がかかって来た。うなだれるように「念のため」持ってきたモバイルを開け、そのあとなんだかんだ言ってTeamsで会議が始まり、対応に巻き込まれ、病室から電話で指示を出し、あっという間に夕方になってしまった。チェッ、明日の手術を控え、もっと自分一人の時間を楽しみたかったのに・・・
でも夕方は、お待ちかね、初めて食べる「病院食」だ。

えっ?ちらし寿司って、「病院食」のイメージと全然違うんだけど・・・もっと何か質素でいかにも病院食って感じを想像していたので、面食らってしまったけど、あぁ、そうか、簡単な外科手術ならそんなカンジの食事でなくてもいいからか、ってそういう状況(大変な思いをしている患者の方々がたくさんいるのに)に感謝をしなければ、と急に神妙な面持ちで食べ始める。ここは病院なのに僕は不謹慎過ぎた。反省しないと。
でも美味しい!味噌汁も美味しい!
きっと、最後に残るのは生理的欲求だけである。ご飯が美味しいと少しでも感じられるだけの身体の機能が残っていたら、人はなかなか死ねないだろう。でも、それさえ無くなったとしても、窓の外の美しい風景を一目見ただけで、まだ生きたいと思うかもしれない。
そんな人間の生への執着と不思議さを、僕はずっと考えている。
「PLAN75」のプランとは勿論、計画のことだ。
計画だって?
人間が計画的に生や死を営んでいるとか、経済活動をやっているとか、歴史を切り開いているとか、本気でそう思うなら、何も見えずに人生を歩いているのでは?と思うのである。
計画だって?
我々はそんな合理的な生き物?
この作品の主人公が見ていた朝焼けが、僕の脳裏にまだ焼き付いている。それはいつか自分が見るかもしれない、死を前にした時の、絶望的で崇高で、不思議な光景である。